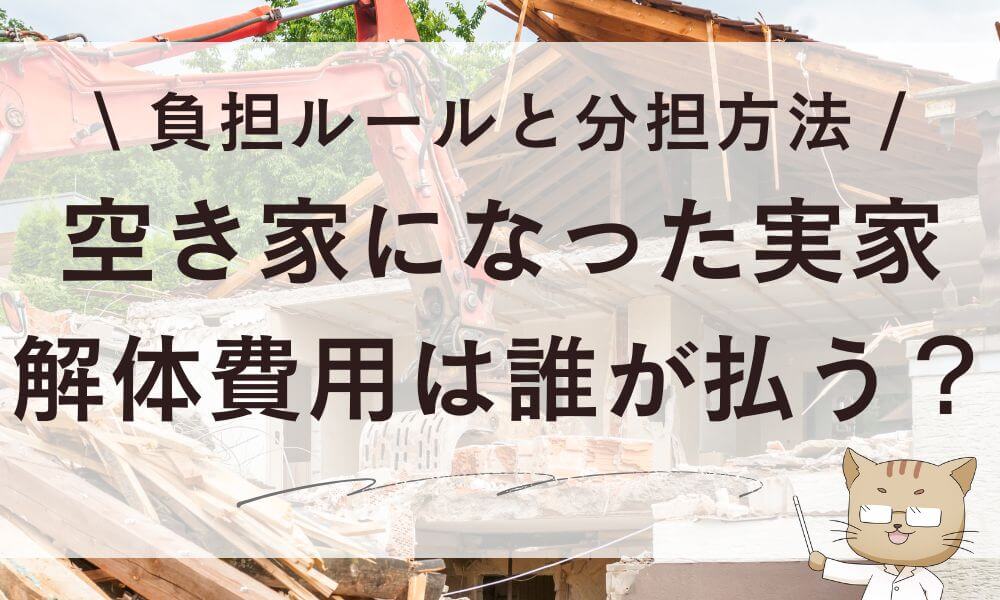
「実家の解体費用、私が全部払うの?」
「兄弟がいるけど誰がいくら負担する?」
「相続放棄すれば費用は払わなくて済む?」
親から相続した実家の老朽化が進み、解体を検討している方からこのような相談をよく受けます。
解体費用は100万円を超えることが多く、突然の負担に困惑するのは当然のことです。
しかし、解体費用の負担者や分担方法について正しく理解せずに進めてしまうと、家族間のトラブルや想定外の費用負担が発生する可能性があります。
そこでこの記事では、不動産×住宅業界のプロが『空き家になった実家の解体費用は誰が払う?負担ルールと分担方法』と題して徹底解説します。
最後まで読めば、解体費用の負担ルールから分担方法、費用を削減する具体的な方法まで理解でき、あなたの状況に合った解決策を選択できるはずです。
- 西田 喜宣(ニシダ ヨシノブ)

-
不動産×住宅業界18年。3,000人以上の売却・購入・住み替えなどをサポート。不動産コンサルティングのクラウドハーツ・リアルエステート代表。ブログ116万PV超 ≫運営者情報
【経歴】大手不動産会社・ハウスメーカー営業15年10ヶ月→現職の代表
【資格】公認 不動産コンサルティングマスター|宅地建物取引士|2級FP技能士
空き家になった実家の解体費用は誰が払う?基本の負担ルール

空き家になった実家の解体費用は、原則として「登記上の所有者」が全額負担するのが基本的なルールです。
相続によって実家を引き継いだ場合、建物の所有権と一緒に解体費用の支払い義務も相続されます。

所有者に責任があるのは
当然といえば当然じゃ!
このルールは民法に基づいており、プラスの財産だけでなく、マイナスの義務も一緒に相続することが法的に定められています。
つまり、実家を相続した瞬間から、その解体費用を支払う責任が発生するということです。

相続って財産だけじゃ
ないんですね
空き家の解体費用は原則「所有者」が負担する
空き家の解体費用を支払う義務があるのは、登記簿謄本に記載されている「所有者」です。
実家を相続した場合、相続登記によって新しい所有者となった方が解体費用を負担することになります。
| 所有者のケース | 解体費用の負担者 |
|---|---|
| 単独相続した場合 | 相続した本人が全額負担する |
| 共同相続した場合 | 持分割合に応じて分担する |
| 生前に贈与された場合 | 贈与を受けた本人が負担する |
| 購入した場合 | 購入者が負担する(契約内容による) |
この責任は、実家を使用していない場合でも変わりません。

住んでなくても
責任があるんですね
空き家を放置していると、近隣への被害や特定空き家への指定リスクもあるため、早めの対応が重要になります。

放置は危険じゃから
しっかり考えるのじゃ!
解体費用の負担義務が発生するタイミングを知る
解体費用の負担義務が発生するタイミングは、所有権が移転した瞬間です。
相続の場合、被相続人が亡くなった時点で自動的に相続が開始され、相続登記を完了すると正式に所有者としての責任が始まります。
- 被相続人の死亡により相続が開始する
- 遺産分割協議で相続人を決定する
- 相続登記で所有権を移転する
- 解体費用の負担義務が確定する
ただし、相続登記前であっても、実際に実家を管理している相続人には管理責任が発生する場合があります。

登記前でも責任が
あるケースがあるんですね
特に、実家に住み続けている方や頻繁に利用している方は、相続放棄をしても管理義務が残る可能性があるため注意が必要です。
さらに、空き家が「特定空き家」に指定されると、行政からの指導や勧告を受ける場合があり、最終的には行政代執行による強制解体とその費用請求のリスクも発生します。

行政代執行って
怖そうです…
以上、空き家の解体費用は所有者が負担するという基本ルールと、その責任が発生するタイミングについて解説しました。
相続による実家の取得は、建物の所有権だけでなく解体費用の負担義務も一緒に引き継ぐことを理解し、早めの対策を検討することが大切です。
[相続人が複数の場合]空き家の実家解体費用の分担方法

相続人が複数いる場合の空き家解体費用は、各相続人の持分割合に応じて分担するのが基本的な考え方です。
ただし、実際の負担方法は遺産分割協議によって決定されるため、相続人全員の合意が必要になります。

みんなで話し合いが
大切ということじゃな!
法律では具体的な分担方法が明確に定められていないため、相続人間でのトラブルが発生しやすいのも現実です。
そのため、解体を進める前に、しっかりとした話し合いと合意形成が欠かせません。

事前の話し合いが
重要なんですね
持分割合に応じて分担費用を計算する
改めて、複数の相続人がいる場合、解体費用は原則として各相続人の持分割合に応じて分担します。
法定相続分や遺産分割で決定した持分に基づいて、費用を按分するのが一般的な方法です。
| 相続パターン | 持分割合の例 | 解体費用120万円の分担例 |
|---|---|---|
| 配偶者と子2人 | 配偶者1/2、子各1/4 | 配偶者60万円、子各30万円を負担する |
| 子3人のみ | 各1/3ずつ | 各40万円ずつ負担する |
| 兄弟2人のみ | 各1/2ずつ | 各60万円ずつ負担する |

計算は意外と
シンプルですね
ただし、経済状況が異なる相続人同士では、平等な負担が困難な場合もあります。
そのような状況では、代わりに実家を単独相続する方が解体費用を全額負担し、他の相続人は相続を放棄するケースも考えられます。

現実的な解決策を
見つけることが大事じゃ!
遺産分割協議で負担方法を決定する
解体費用の具体的な分担方法は、遺産分割協議の中で相続人全員が合意して決定します。
持分割合による分担が基本ですが、相続人の経済状況や実家への思い入れなどを考慮して、柔軟に調整することも可能です。
- 持分割合に完全に準拠して分担する
- 経済力のある相続人が多めに負担する
- 実家に愛着のある相続人が全額負担する
- 解体せずに一人が単独相続する
- 実家を売却して売却代金から費用を差し引く

いろんな方法が
あるんですね
遺産分割協議では、解体のタイミングや業者選定についても併せて決定することが重要です。
後々のトラブルを避けるため、話し合いの内容は必ず遺産分割協議書に明記しておきましょう。
トラブルを避けるポイントを押さえる
複数相続人での解体費用分担では、事前の準備とコミュニケーションがトラブル回避の鍵となります。
まず、解体費用の見積もりを複数の業者から取得して、正確な費用を把握することから始めましょう。
| トラブル要因 | 対策方法 |
|---|---|
| 費用負担への不満 | 事前に詳細な見積もりを共有する |
| 解体時期の意見対立 | 維持費用も含めて比較検討する |
| 業者選定での対立 | 相見積もりを取り透明性を確保する |
| 支払い方法の不一致 | 一括払いか分割払いかを事前協議する |
さらに、相続人の中に経済的に厳しい方がいる場合は、補助金制度や解体ローンの活用も検討材料として提示しましょう。

みんなが納得できる
方法を探すことですね
また、解体工事中の近隣対応や工事完了後の土地の活用方法についても、事前に話し合っておくことで、後々の責任の所在を明確にできます。

最後まで責任を持って
進めることが肝心じゃ!
以上、複数の相続人がいる場合の解体費用分担方法について、基本的な考え方から具体的なトラブル回避策まで詳しく解説しました。
家族間での話し合いは感情的になりがちですが、客観的な情報を共有し、全員が納得できる解決策を見つけることが、円満な問題解決への近道となります。
[相続放棄した場合]実家の解体費用の負担は誰が払う?

相続放棄をしても、実家の解体費用の支払い義務が完全になくなるわけではありません。
民法では、相続放棄をした場合でも「保存義務」が発生するケースがあり、実際に実家を管理していた相続人には管理責任が残る可能性があります。

相続放棄は万能薬
ではないということじゃ!
つまり、相続放棄したからといって、必ずしも解体費用を免れられるとは限らないのが現実です。
相続放棄を検討する際は、この点をしっかりと理解しておくことが重要になります。

思っていたより
複雑なんですね
相続放棄しても管理義務が残るケースを理解する
相続放棄をしても解体費用の負担が残るのは、実際に実家を使用・管理していた相続人です。
民法では、相続放棄をした者であっても、相続財産の管理を継続する義務が課される場合があると定めています。
| 管理義務が残りやすいケース | 管理義務が残りにくいケース |
|---|---|
| 被相続人と同居していた | 実家に一度も住んだことがない |
| 実家を頻繁に利用していた | 年に数回程度しか訪問しない |
| 実家の鍵を管理していた | 実家の鍵を持っていない |
| 実家の維持管理を担当していた | 実家の管理に一切関与していない |

実際の関わり方が
ポイントなんですね
特に注意すべきは、相続放棄後も実家に住み続けている場合です。
この場合、実質的な管理者とみなされ、解体費用の支払い義務が継続する可能性が高くなります。

住み続けるなら
覚悟が必要ですね…
また、他に相続人がいない場合や、全員が相続放棄した場合でも、相続財産清算人が選任されるまでの間は管理義務が残ります。

最後まで責任を持たなければ
ならん場合があるのじゃ!
相続財産清算人制度を活用する
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることで、解体費用の負担を回避できる可能性があります。
相続財産清算人は、弁護士などの専門家が選任され、実家を含む相続財産の管理・清算を行います。
- 利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行う
- 裁判所が相続財産清算人を選任する
- 相続財産清算人が実家を売却または管理する
- 売却代金から解体費用を支払う
- 残った財産を国庫に帰属させる

専門家に任せられるなら
安心ですね
ただし、相続財産清算人の選任には数十万円から100万円程度の予納金が必要になります。
この予納金は、相続財産清算人の報酬や管理費用に充てられるもので、相続財産から回収できない場合は申立人の負担となります。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 申立手数料 | 800円(収入印紙) |
| 予納金 | 50万円~100万円程度 |
| 清算人報酬 | 財産額に応じて決定 |
| 管理費用 | 実際にかかった費用 |

結構な費用が
かかるんですね!
また、手続きには時間がかかるため、その間の実家の管理責任は申立人に残ることも理解しておく必要があります。

時間とお金の両方が
必要ということじゃ!
相続放棄の注意点とリスクを把握する
相続放棄を検討する際は、解体費用の負担回避だけでなく、総合的な影響を慎重に検討することが大切です。
相続放棄は一度行うと撤回できないため、後悔のない決断をする必要があります。
- プラスの財産もすべて放棄することになる
- 他の相続人に負担が集中する可能性がある
- 管理義務が残る場合は費用負担が継続する
- 相続放棄の期限を3カ月以内に守る必要がある
- 撤回や取り消しは原則として認められない

一度決めたら
戻れないんですね…
特に、実家に思い出がある場合や、将来的に活用したい場合は、相続放棄以外の解決策も併せて検討しましょう。
解体費用の補助金制度や解体ローンの活用、実家の売却など、様々な選択肢があります。

他の方法も含めて
考えた方が良さそうです
また、相続放棄をする場合でも、実家の状況悪化による近隣トラブルや損害賠償のリスクは残る可能性があります。
定期的な点検や最低限の管理は継続する必要があることを覚えておきましょう。

完全に手を離せるわけでは
ないということじゃな!
以上、相続放棄をした場合の実家解体費用負担について、管理義務の継続から相続財産清算人制度の活用まで幅広く解説しました。
相続放棄は簡単な解決策に思えますが、実際には多くの制約や注意点があるため、専門家への相談を含めて慎重な判断が求められる重要な決断といえるでしょう。
また、空き家をそのままにしておくリスクや対策について詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。
「空き家をそのままにして大丈夫?」 「放置すると法的問題になる?」 「近隣に迷惑をかけてしまう?」 相続や転居により空き家を所有することになった方の多くが、このような不安を抱えています。 実際、全国レベルで年々空き家が増 …
空き家になった実家の解体費用を安くする4つの方法

空き家の解体費用は100万円を超えることが多く、家計にとって大きな負担となります。
しかし、適切な方法を知っていれば、解体費用を大幅に削減することは十分可能です。
- 複数の解体業者の見積もりを必ず取る
- 自治体の解体補助金制度を活用する
- 解体工事の時期を閑散期に合わせる
- 解体せずに「現状のまま」で売却する

4つの方法を
詳しく知りたいです
1.複数の解体業者の見積もりを必ず取る
解体費用を抑える最も確実な方法は、複数の解体業者から相見積もりを取ることです。
同じ建物でも業者によって解体費用に30万円~50万円の差が生じることは珍しくありません。

業者によって価格差が
こんなにあるとは驚きじゃ!
| 見積もり業者数 | 費用削減の期待値 | 最安値を見つける確率 |
|---|---|---|
| 1社のみ | 削減効果なし | 20%程度 |
| 3社で比較 | 10万円~30万円 | 60%程度 |
| 5社以上で比較 | 20万円~50万円 | 80%以上 |
複数の業者に依頼することで、適正価格の把握と価格交渉の材料を得ることができます。

複数社に依頼すると
こんなにメリットがあるんですね
見積もりを依頼する際は、解体範囲や廃材処理方法、工期などの条件を統一して比較することが重要です。
また、極端に安い見積もりには追加費用の発生リスクがあるため、内訳をしっかりと確認しましょう。

安すぎる業者には
気をつけることじゃ!
2.自治体の解体補助金制度を活用する
多くの自治体では、空き家問題の解決を目的とした解体費用の補助金制度を設けています。
補助金額は自治体によって異なりますが、一般的には解体費用の1/3~1/2、上限50万円程度の補助を受けることができます。
- 老朽化した空き家を対象として申請する
- 一定期間以上使用されていない建物に適用される
- 所有者本人または相続人が申請できる
- 解体工事着手前に申請を行う必要がある
- 予算の範囲内で先着順となる場合が多い

50万円も補助してもらえるなら
助かりますね
補助金の申請は年度初めに受付が開始され、予算がなくなり次第終了するため、早めの申請が重要です。
申請条件や必要書類は自治体によって異なるため、まずは建築指導課や都市計画課に問い合わせて詳細を確認しましょう。

早めの行動が
大切なんですね
また、補助金の交付決定前に解体工事を開始すると対象外となる場合があるため、必ず事前申請を行うことを忘れないでください。

手順を守ることが
肝心じゃな!
3.解体工事の時期を閑散期に合わせる
解体工事には繁忙期と閑散期があり、閑散期に工事を依頼することで費用を抑えることができます。
一般的に、1月~3月と6月~8月は解体工事の閑散期とされ、繁忙期と比較して10%~20%程度安くなる傾向があります。
| 時期 | 特徴 | 費用への影響 |
|---|---|---|
| 1月~3月 | 新年度前の静かな時期 | 10%~15%安くなる |
| 4月~5月 | 新築ラッシュで繁忙 | 通常価格または高め |
| 6月~8月 | 梅雨・猛暑で工事が少ない | 15%~20%安くなる |
| 9月~12月 | 年末までの駆け込み需要 | 通常価格または高め |

時期を選ぶだけで
こんなに違うんですね
ただし、閑散期を狙う場合は天候による工事の遅れや品質への影響も考慮する必要があります。
特に梅雨時期は雨天による作業中断が発生しやすく、工期が延びる可能性があることを理解しておきましょう。

天候のリスクも
考えないといけませんね
また、複数の業者に相見積もりを依頼する際も、閑散期であればより丁寧な対応と柔軟な価格交渉が期待できます。

時期と複数社への依頼を
組み合わせるのが賢いやり方じゃ!
4.解体せずに「現状のまま」で売却する
解体費用を完全に回避する方法として、実家を解体せずに現状のまま売却することも有効な選択肢です。
古家付き土地として売却すれば、解体費用をかけずに実家を手放すことができます。
- 解体費用を負担する必要がない
- 買主が解体するか活用するかを選択できる
- 売却代金をそのまま受け取ることができる
- 固定資産税の負担からも解放される
- 管理の手間と費用を削減できる

解体しなくても
売れるんですね
ただし、現状売却の場合は更地と比較して売却価格が安くなる可能性があります。
築年数が古い建物の場合、土地の価値から解体費用相当額を差し引いた価格での取引となることが一般的です。

価格は下がっても
手間を考えると良い方法ですね
売却が困難な場合は、不動産買取業者への相談も検討しましょう。
買取業者であれば、古い建物でも現状のまま買い取ってもらえる可能性が高く、最短1週間程度で現金化することも可能です。

買取業者なら確実性が
高いということじゃな!
空き家の売却方法や高く売るためのコツについて詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。
「空き家の維持管理がもう限界…」 「古い空家でも本当に売れるの?」 「売却手続きが複雑すぎてわからない」 このような悩みを抱えている方は決して少なくありません。 実際に、相続や転勤などにより空き家を所有することになった方 …
以上、空き家の解体費用を安くする4つの方法について、それぞれの特徴と注意点を含めて詳しく紹介しました。
これらの方法を組み合わせることで、解体費用の大幅な削減や負担の回避が可能になり、相続した実家の問題をより現実的に解決できるはずです。
まとめ:空き家の解体費用で悩んだら専門家に相談を

今回の不動産とーくは『空き家になった実家の解体費用は誰が払う?負担ルールと分担方法』と題して、下記の項目を解説しました。
- 空き家になった実家の解体費用は誰が払う?基本の負担ルール
- [相続人が複数の場合]空き家の実家解体費用の分担方法
- [相続放棄した場合]実家の解体費用の負担は誰が払う?
- 空き家になった実家の解体費用を安くする4つの方法
- まとめ:空き家の解体費用で悩んだら専門家に相談を

疑問は解決できたかの~?
空き家の解体費用問題は、多くの方が直面する深刻な悩みです。
100万円を超える費用負担、複雑な相続関係、法的責任など、一人で抱え込むには重すぎる問題だと思います。

本当に大変な
問題ですよね
だからこそ、適切な専門家への相談が何よりも重要になります。
解体費用の負担で悩んでいる方は、まず以下の専門家に相談することをおすすめします。
相談すべき専門家を選択する
空き家の解体費用問題は複数の分野にまたがるため、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。
相続や法的な問題については司法書士や弁護士、費用負担については税理士、解体そのものについては解体業者や不動産会社への相談が効果的です。

どの専門家に相談すればいいか
迷ってました
また、自治体の窓口では補助金制度や空き家バンクなどの公的支援について詳しい情報を得ることができます。
多くの自治体では空き家相談窓口を設置しており、無料で相談に応じてくれるケースも多いです。

まずは自治体に相談してみる
のも良いアイデアじゃ!
一人で悩まずに早めの行動を取る
空き家の問題は時間が経つほど状況が悪化し、解決が困難になります。
建物の老朽化が進めば解体費用が高くなり、近隣トラブルや特定空き家への指定リスクも高まってしまいます。

放置すると状況が
悪くなる一方ですね
だからこそ、早めに専門家に相談し、現実的な解決策を見つけることが重要です。
解体以外にも売却や活用など、様々な選択肢があることを知れば、きっと最適な解決方法が見つかるはずです。

選択肢があると知って
少し安心しました
また、家族間での話し合いが必要な場合も、専門家の助言があれば感情的にならずに冷静な判断ができるでしょう。

専門家のサポートがあれば
心強いものじゃ!
空き家の解体費用で悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、ぜひ専門家の力を借りて問題の解決に向けて行動を起こしてください。
きっと、あなたとご家族にとって最良の解決策が見つかり、安心して毎日を過ごせるようになるはずです。
以上『空き家になった実家の解体費用は誰が払う?負担ルールと分担方法』でした。
この記事を読んだ人には下記もおすすめです。
ぜひあわせてチェックしてみて下さい。
「思い出がつまった実家を壊すなんて…」 「何十年も住んだ家がなくなるなんて…」 実家の解体を決断したものの、胸が締め付けられるような寂しさを感じていませんか? 私も不動産アドバイザーとして、多くの方から「どうしても寂しい …
「空き家なのに会費請求された…」 「会費って支払い義務があるの?」 「断ったらトラブルになるのかな?」 相続や転居で空き家を所有することになり、突然町内会費や自治会費の支払いを求められて困惑している方は意外に多いものです …
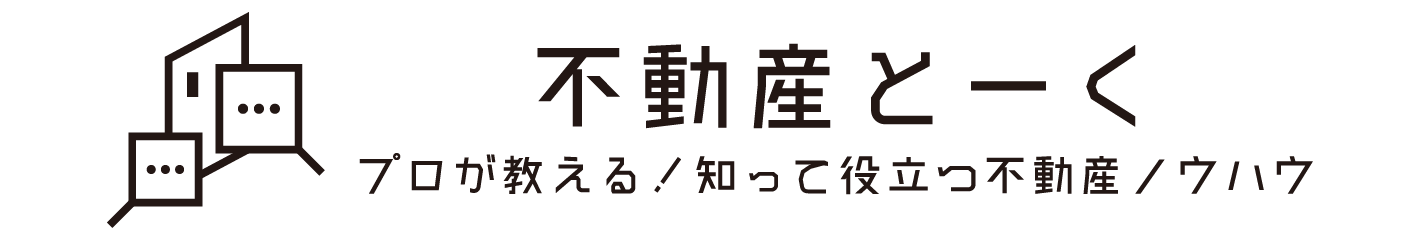

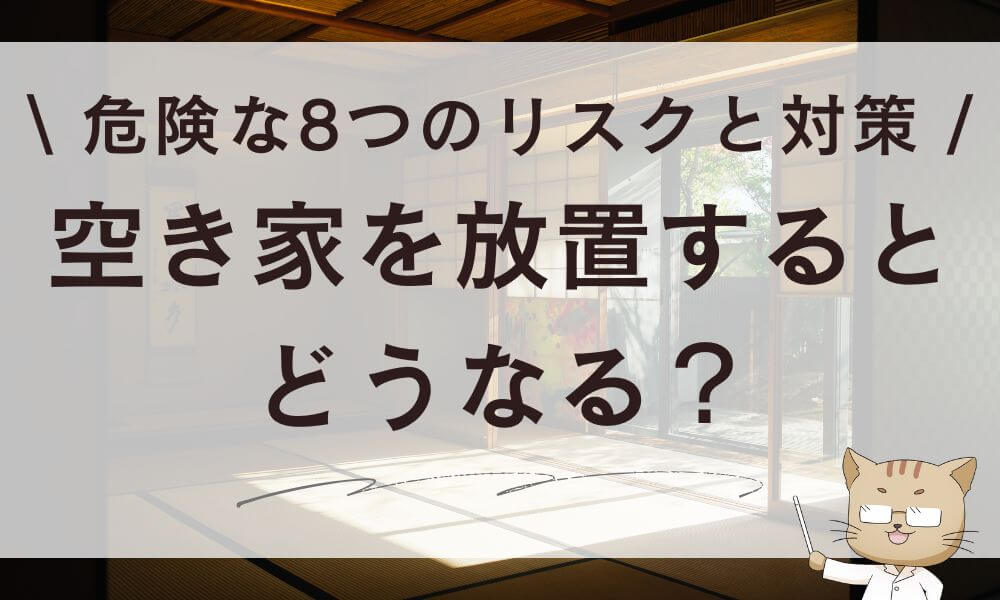
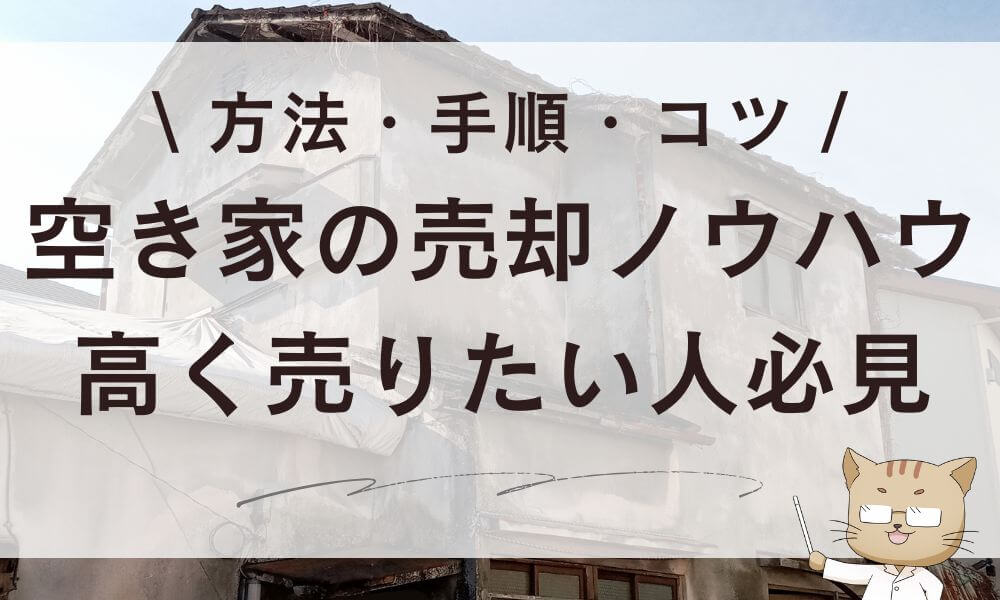

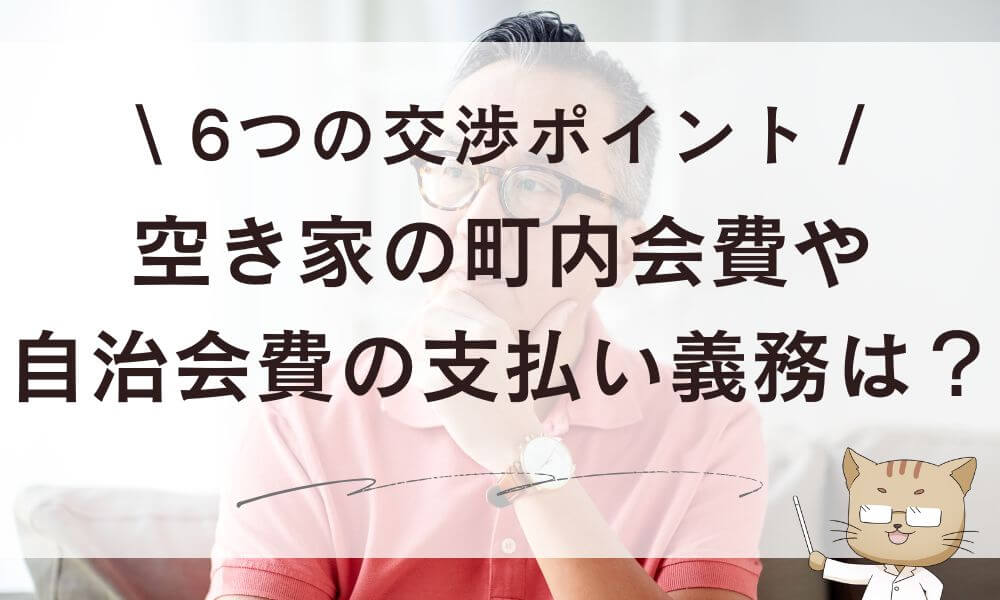
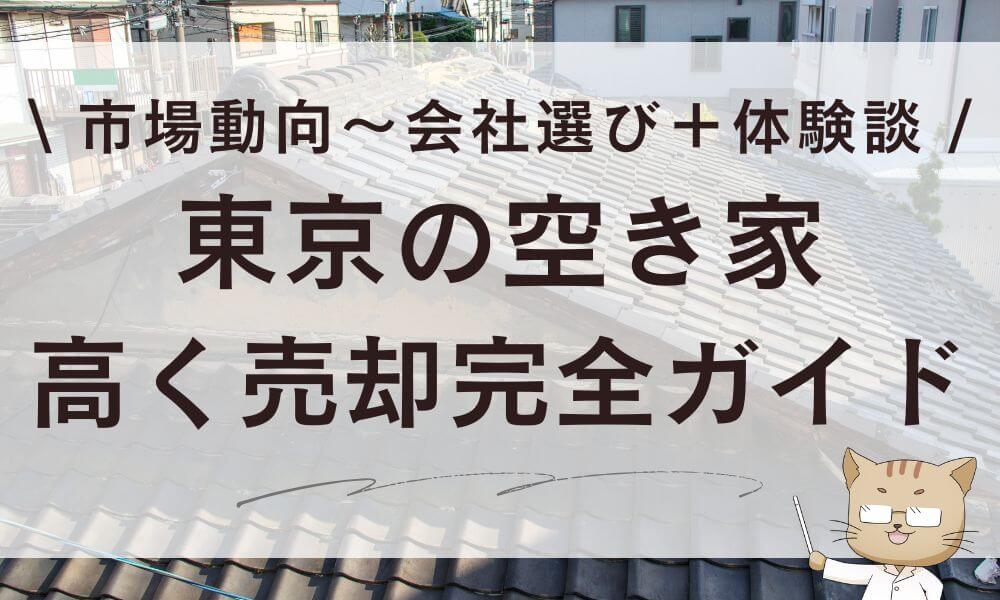
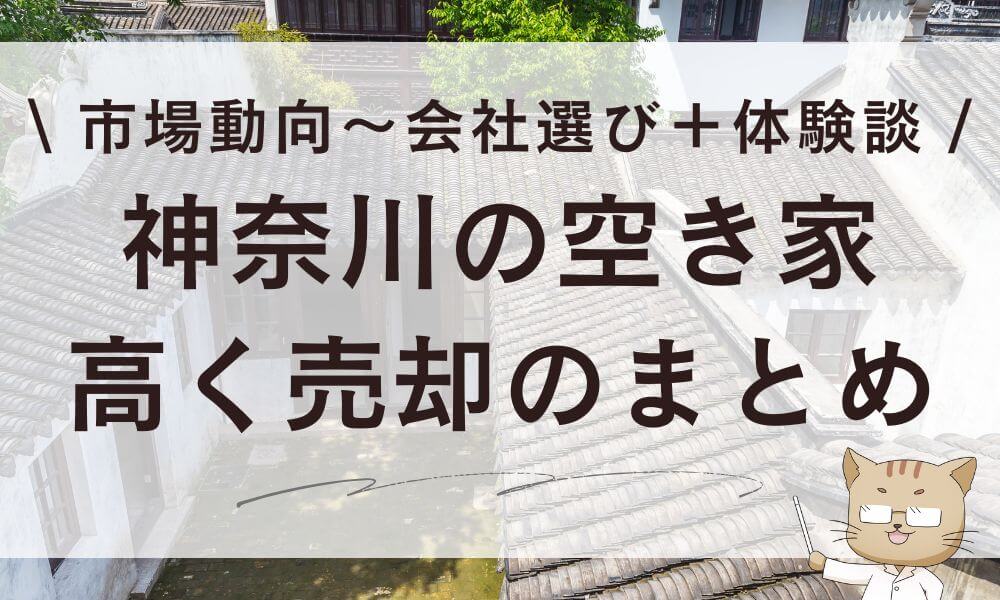
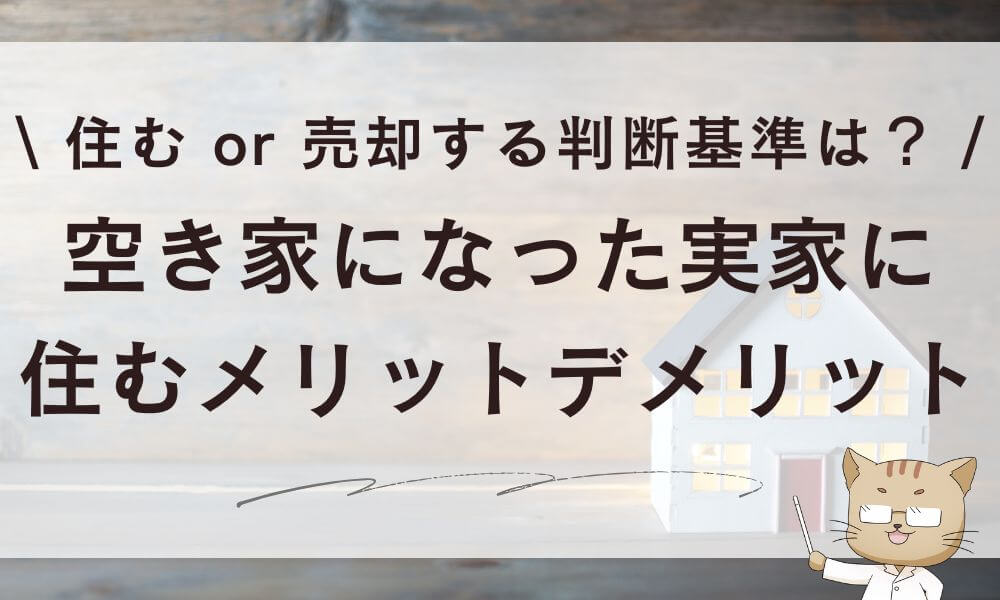
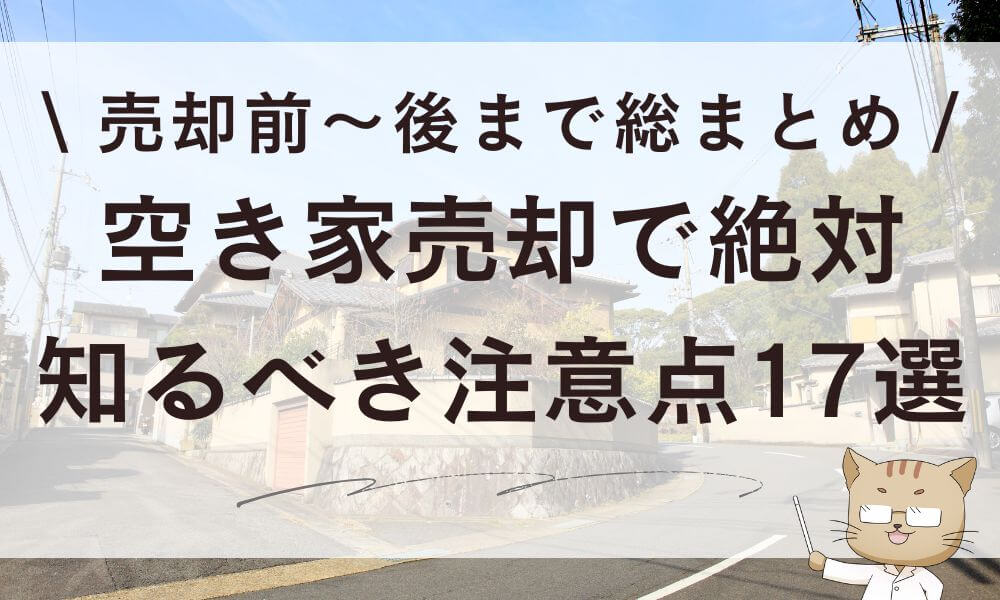
![[体験談]実家売却で後悔した人・しなかった人!5つの事前準備は?](https://realestate-talkbar.jp/wp-content/uploads/2025/08/i0660.jpg)